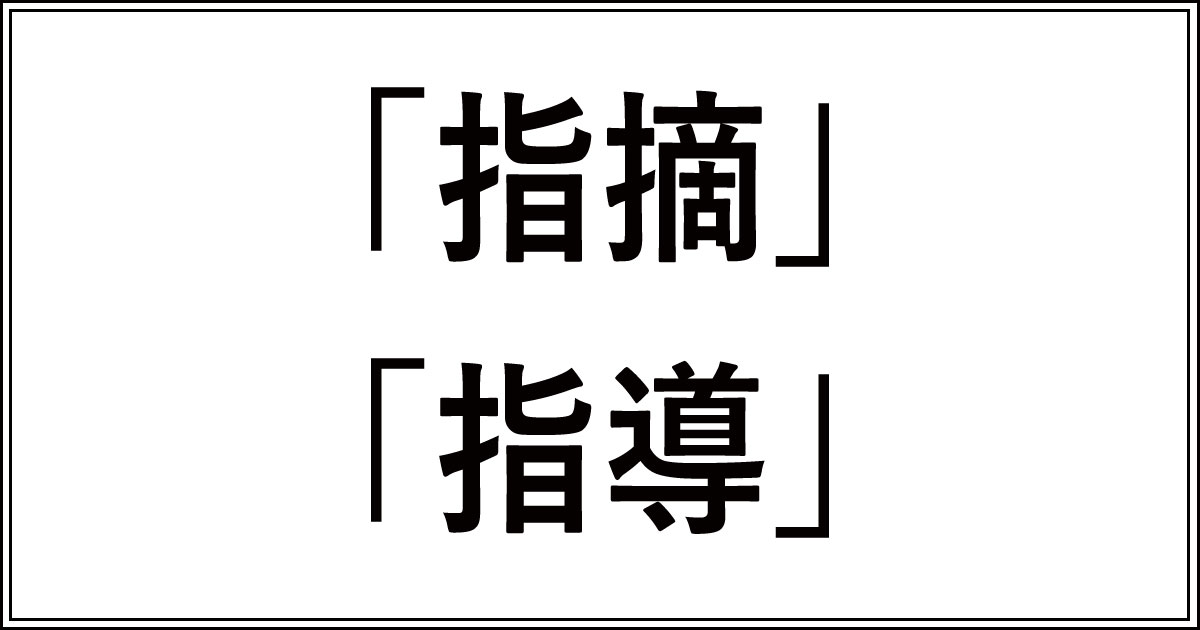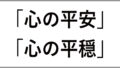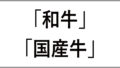「部下に指摘しました」と「部下を指導しました」、どちらが正しい表現か迷ったことはありませんか?職場でよく使われる「指摘」と「指導」という言葉ですが、実は明確な違いがあるんです。この違いを理解せずに使っていると、相手に誤解を与えたり、適切なコミュニケーションが取れなくなる可能性があります。
私自身も子育てをしていて、子どもに対して「これは違うよ」と伝える時、ただ問題を指し示すだけでなく、なぜそうなのか、どうすれば良いのかまで説明するように心がけています。これこそが「指摘」と「指導」の違いなんです。
この記事では、日常生活やビジネスシーンで正しく使い分けられるよう、「指摘」と「指導」の意味の違いから具体的な例文、使い分けのポイントまで、分かりやすく解説していきます。
「指摘」の基本的な意味とは?
「指摘」とは、問題点や間違い、注意すべき点を具体的に取り上げて指し示すことです。英語でいうと「point out」に近い意味になります。
指摘の特徴
指摘には以下のような特徴があります:
問題を示すだけ 指摘は単に問題を指し示すだけにとどまる表現で、その後の解決策や改善方法までは含まれません。「ここが間違っています」「この部分に問題があります」といったように、事実を伝えることが主な目的です。
具体的で客観的 指摘は具体的な事実に基づいて行われます。感情的になったり、個人的な意見を述べるのではなく、客観的な視点から問題点を明確にします。
一時的な行為 指摘は一回限りの行為として行われることが多く、継続的な関わりは含まれません。
指摘を使った例文
- 「資料の計算に間違いがあることを指摘した」
- 「会議で予算の問題点を指摘された」
- 「先生から宿題の漏れを指摘された」
- 「お客様から商品の不具合を指摘された」
「指導」の基本的な意味とは?
一方、「指導」とは、目的や方向に沿って教え導くことを意味します。英語では「guide」や「lead」に相当する言葉です。
指導の特徴
指導には以下のような特徴があります:
教え導く行為 ミスなどを取り上げるだけでなく、その後の方針をアドバイスしたり提案したりすることも含まれます。問題を見つけたら、それをどう解決すべきかまで示すのが指導です。
継続的な関わり 指導は一度きりではなく、継続的に相手の成長を支援する行為です。相手ができるようになるまで見守り、サポートを続けます。
責任を伴う 指導する方が責任を持っているかどうかが重要で、相手の成長に対して責任を持つ姿勢が求められます。
指導を使った例文
- 「新入社員に営業の指導を行った」
- 「コーチから技術面の指導を受けた」
- 「部下の業務改善について指導する」
- 「子どもの勉強を指導する」
パワハラ・モラハラ加害者は人をバカにする。
— ムート パワハラ モラハラに悩む人へ (@mutpawa) June 17, 2025
相手を笑いものにして自分を大きく見せる。
人のミスを大声で指摘し、恥をかかせる。
指摘と指導の根本的な違い
では、「指摘」と「指導」の根本的な違いは何でしょうか?主要な違いを整理してみましょう。
目的の違い
指摘の目的 問題や間違いを相手に知らせること。「これが問題です」と事実を伝えるのが主な目的です。
指導の目的 相手の成長や改善を促すこと。問題を解決し、より良い状態に導くことが目的です。
関わり方の違い
指摘の関わり方 一方的に情報を伝える関係。指摘する側は問題を伝えるだけで、その後の対応は相手に任せます。
指導の関わり方 双方向的なコミュニケーション。指導する側は相手の理解度を確認しながら、継続的にサポートします。
責任の範囲
指摘の責任 事実を正確に伝える責任はありますが、その後の改善については責任を負いません。
指導の責任 相手が改善できるよう継続的にサポートし、成長に対して責任を持ちます。
ビジネスシーンでの使い分け方
職場では「指摘」と「指導」を適切に使い分けることが重要です。状況に応じた使い分けのポイントを見てみましょう。
指摘を使うべき場面
緊急性がある場合 「この書類に誤字があります」「データに間違いがあります」など、すぐに修正が必要な問題を伝える時は指摘が適切です。
同僚や対等な関係の場合 「会議の時間が変更になったことをお伝えします」のように、情報共有の意味合いが強い場合は指摘を使います。
客観的事実を伝える場合 感情を交えず、事実のみを伝える必要がある場合は指摘が適しています。
指導を使うべき場面
部下や後輩との関係 「この業務のやり方について指導します」のように、継続的な関わりが必要な場合は指導を使います。
成長を促したい場合 相手のスキルアップや能力向上を目的とする場合は、指導が適切です。
教育的な意味合いがある場合 なぜそうすべきなのか、どうすれば改善できるのかを教える場合は指導を選びます。
実際の例文で比較
指摘の例
- 「プレゼン資料の5ページ目にグラフの間違いがあることを指摘させていただきます」
- 「会議の開始時刻に遅れていることをご指摘申し上げます」
指導の例
- 「プレゼン資料の作成方法について指導いたします。まず構成から一緒に考えましょう」
- 「時間管理について指導します。スケジュール帳の使い方から始めましょう」
「ご指摘」と「ご指導」の敬語表現
ビジネスシーンでは、敬語を使った「ご指摘」と「ご指導」もよく使われます。それぞれの正しい使い方を確認しましょう。
ご指摘の使い方
ご指摘は、自分以外の人が指摘をすることに対して敬意を示す言葉です。自分が指摘を受けた時に使用します。
正しい使用例
- 「貴重なご指摘をありがとうございます」
- 「ご指摘の通り、修正いたします」
- 「ご指摘いただいた点について検討いたします」
間違った使用例
- 「私がご指摘いたします」(自分が指摘する時には使わない)
ご指導の使い方
「ご指導」は、相手から継続的な教えや導きを受ける際に使用します。
正しい使用例
- 「今後ともご指導のほど、よろしくお願いいたします」
- 「ご指導いただき、ありがとうございました」
- 「ご指導を賜りたく存じます」
子育てや教育現場での使い分け
家庭や学校などの教育現場でも、「指摘」と「指導」の使い分けは重要です。私自身の子育て経験を踏まえながら解説します。
効果的な子どもへの接し方
指摘だけでは不十分 「宿題をしていない」「部屋が散らかっている」といった問題を指摘するだけでは、子どもは どうすれば良いのか分からず、同じことを繰り返してしまいます。
指導で成長を促す 「宿題は毎日決まった時間にやることで、習慣が身につくよ。一緒にスケジュールを作ってみよう」のように、理由を説明し、具体的な解決方法を示すことで、子どもの成長につながります。
実際の場面での使い分け
朝の支度が遅い場合
- 指摘:「支度が遅いよ」
- 指導:「支度が遅いと困ることを一緒に考えよう。明日からは時計を見ながら、この時間までに着替えを終わらせようね」
勉強に集中できない場合
- 指摘:「集中していない」
- 指導:「集中するコツを教えるよ。まず机の上を片付けて、時間を決めて取り組んでみよう」
どうしても強めの指導をしなければならない時に、始めにこのような声かけをしてから話をしています。
— トモ (@tomotomo_sensei) June 20, 2025
①今から大切な話をします
②今から耳の痛くなる話をします
③真剣に話すので真剣に聴いてください
④机の上を片付けましょう
叱るというよりも、真剣に伝えることを心がけています。 pic.twitter.com/CL4DzSv807
よくある間違いと注意点
「指摘」と「指導」を使う際によくある間違いと、注意すべきポイントをまとめました。
よくある間違い
感情的な指摘 指摘は客観的事実を伝えるものなのに、感情的になって相手を責めるような言い方をしてしまうことがあります。これは指摘ではなく、批判や非難になってしまいます。
指導のつもりが指摘だけ 「指摘」をし、「指示」を出しているが、「指導」は行っていないケースがよくあります。問題を指摘し、「直しなさい」と指示するだけでは、真の指導にはなりません。
指摘と指導の混同 どちらを使うべきか迷った時は、「相手の成長を継続的にサポートするか」を基準に判断しましょう。
注意すべきポイント
相手の立場を考慮する 同じ内容でも、相手との関係性や状況によって、指摘と指導のどちらが適切かが変わります。
建設的な姿勢を保つ 指摘する際も指導する際も、相手を責めるのではなく、改善を目的とした建設的な姿勢を保つことが大切です。
継続性を意識する 指導を選んだ場合は、一度きりではなく継続的にサポートする覚悟を持ちましょう。
場面別・具体的な使い分け例
実際の生活やビジネスシーンで使い分けができるよう、具体的な例をご紹介します。
オフィスでの使い分け
会議での使い分け
- 指摘:「資料の3ページ目の数字に誤りがあります」
- 指導:「効果的な資料作成の方法について説明します。データの見せ方にはコツがあります」
部下とのコミュニケーション
- 指摘:「報告書の提出が期限を過ぎています」
- 指導:「報告書の書き方と、期限管理の方法について一緒に考えましょう」
家庭での使い分け
子どもの勉強
- 指摘:「この計算が間違っています」
- 指導:「算数の問題の解き方を一緒に練習しよう。この方法でやってみて」
家事の分担
- 指摘:「洗濯物が干されていません」
- 指導:「効率的な家事の進め方を教えるよ。スケジュールを作って分担しよう」
学校での使い分け
先生から生徒へ
- 指摘:「宿題の提出漏れがあります」
- 指導:「勉強の計画の立て方と、宿題を忘れない方法を教えます」
友人同士
- 指摘:「テストの答えが違っているよ」
- 指導:「この分野の勉強方法を教えるよ。一緒に復習しよう」
相手に与える印象の違い
「指摘」と「指導」では、相手に与える印象が大きく異なります。この違いを理解して使い分けることで、より良い人間関係を築くことができます。
指摘が与える印象
客観的で公平 感情を交えずに事実を伝えるため、客観的で公平な印象を与えます。
一時的な関わり 問題を伝えるだけなので、その後の関係性についてはあまり期待されません。
距離感がある 必要最小限の情報交換という印象で、親密さはあまり感じられません。
指導が与える印象
親身で協力的 相手の成長を願い、継続的にサポートする姿勢が伝わります。
信頼関係の構築 長期的な関わりを前提とするため、信頼関係の構築につながります。
温かみがある 相手のことを思いやる気持ちが伝わり、温かい印象を与えます。
よくある質問(FAQ)
Q1: 「指摘」と「指導」、どちらを使うべきか迷った時はどうすればいいですか?
A1: 相手との関係性と目的を考えてみましょう。一度きりの情報共有であれば「指摘」、相手の成長を継続的にサポートしたい場合は「指導」を選びます。迷った時は、「この後も関わり続けるか」を基準に判断してください。
Q2: 同僚に対して「指導」を使うのは適切でしょうか?
A2: 同僚に対しては基本的に「指摘」を使う方が適切です。「指導」は上下関係がある場合に使われることが多いためです。ただし、同僚から「教えてほしい」と頼まれた場合や、プロジェクトリーダーとしての立場である場合は「指導」も適切です。
Q3: 自分が間違いを犯した時、どのように表現すればいいですか?
A3: 自分の間違いについては「ご指摘いただき」を使います。例:「ご指摘いただいた通り、計算に誤りがございました」「貴重なご指摘をありがとうございます」
Q4: 子どもに対しては「指摘」と「指導」のどちらが効果的ですか?
A4: 子どもに対しては「指導」の方が効果的です。単に問題を指摘するだけでは子どもは改善方法が分からず、同じ間違いを繰り返してしまいます。なぜダメなのか理由を説明し、どうすれば良いのか具体的に教える「指導」を心がけましょう。
Q5: ビジネスメールでは「ご指摘」と「ご指導」のどちらを使うべきですか?
A5: 状況によって使い分けます。相手から問題点を教えてもらった場合は「ご指摘」、継続的なアドバイスをもらった場合は「ご指導」を使います。迷った場合は「ご指摘・ご指導いただき」のように両方を使う方法もあります。
「言葉」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ:指摘と指導の違いを理解して適切に使い分けよう
「指摘」と「指導」の違いについて詳しく解説してきました。最後に重要なポイントをまとめておきましょう。
指摘と指導の基本的な違い
- 指摘:問題点や間違いを指し示すだけ。一時的で客観的な行為
- 指導:問題を指摘した上で、改善方法を教え、継続的にサポートする行為
使い分けの基準
- 一度きりの情報共有→「指摘」
- 継続的な成長支援→「指導」
- 同僚や対等な関係→「指摘」
- 上下関係がある場合→「指導」
敬語表現での注意点
- 「ご指摘」:相手から指摘を受けた時に使用
- 「ご指導」:相手から継続的な教えを受ける時に使用
相手に与える印象の違い
- 指摘:客観的で距離感がある
- 指導:親身で協力的、温かみがある
私自身も子育てや日常生活で、この違いを意識するようになってから、相手とのコミュニケーションがスムーズになったと感じています。単に「間違っている」と伝えるだけでなく、「どうすれば良いか」まで一緒に考えることで、相手との信頼関係も深まります。
言葉の使い分けは、相手への思いやりの表現でもあります。場面や関係性に応じて適切に使い分けることで、より良いコミュニケーションを築いていきましょう。「指摘」と「指導」の違いを理解し、日常生活やビジネスシーンで活用してみてくださいね。