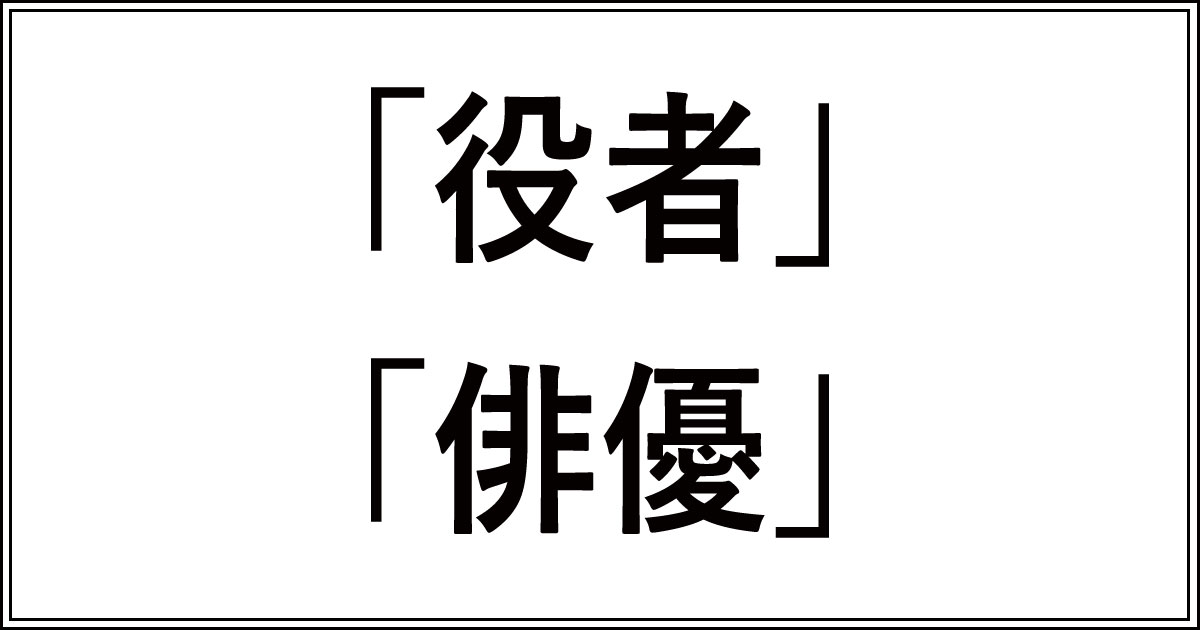「あの人は素晴らしい役者だね」「人気俳優の最新作が話題になっている」など、日常会話でよく耳にする「役者」と「俳優」という言葉。同じような意味で使われることが多いですが、実は微妙な違いがあることをご存知でしょうか?
私も子供の頃は「どちらも同じ意味じゃないの?」と思っていましたが、よく調べてみると、それぞれに独特の歴史や使われ方があることがわかりました。映画やドラマを観る時、どちらの言葉を使うか迷った経験がある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「役者」と「俳優」の違いについて、歴史的背景から現代の使い分け方まで、わかりやすく解説していきます。例文もたくさん紹介するので、明日から自信を持って使い分けができるようになりますよ。
関連記事
「俳優」と「女優」の違い!いつから俳優と呼びだした?
「俳優」と「声優」の違い!仕事内容やスキルや活動場所
役者と俳優の基本的な意味の違い
役者とは何か
役者の主な意味は、「能楽や歌舞伎、芝居などで登場人物を演じる人」というものです。もともとの意味は、「ある役目をする人」というもので、寺院での諸役や法会などの際、特定の担当職務にあたる人を指す言葉でした。
役者という言葉は、戦国時代~江戸時代初期に流行しはじめた歌舞伎にも、引き継がれました。こうしたことから、能や狂言、歌舞伎といった舞台上で役を演じる者のことを「役者」と呼ぶことが定着したといわれているのです。
つまり、役者は日本の伝統的な演劇文化と深く結びついた言葉なのです。
俳優とは何か
一方、俳優という言葉は、テレビドラマ、映画、舞台といったケースで演技をする人たちのことを指しています。より現代的で、幅広いメディアで活躍する演技者を表す言葉として使われています。
興味深いのは、俳優は奈良時代以前から使われている言葉であるが、俳優と書いて「わざおぎ」と読んだ。「わざ」は神意や神霊、「おぎ」はヲグ(=招く)の名詞形を意味している。すなわち俳優とは本来、滑稽な踊りや歌などによって神の力を招き寄せること・人のことであり、現在の「演じる」という意味はなかったという点です。
現代における違い
現在では、両者の意味は同じと考えられている。古くからある演劇(歌舞伎・能など)を演じる人に対して「役者」を用いることが多いものの、実際にどちらを用いるかは個人の考え方によるところが大きい。
『国宝』観てきました。
— 吉高 志音 STAFF (@sionyoshitaka) July 3, 2025
とんでもない作品でした。
上手く言葉にできないくらい。本当に天晴れ。
役者が生きる"本物"を見せてもらいました。
まだ観てない方はぜひ!#国宝#映画国宝 pic.twitter.com/bbN2gZqKds
歴史的背景から見る役者と俳優
役者の歴史
役者という言葉の歴史を紐解くと、歌舞伎は俳優の芸を中心として成り立つ演劇であった。したがって、俳優が歌舞伎の構造の上に占める位置は極めて大きかった。しかし、社会的には河原者・河原乞食などと呼ばれ、士農工商の四民以下に属させられていた。彼らは一般には〈役者〉と呼ばれた。
つまり、役者は江戸時代から続く伝統的な呼び方で、社会的地位は低かったものの、民衆からは愛されていた存在だったのです。
俳優の歴史
俳優という言葉は、同時に海外の演劇が国内で上演されるようになった明治時代に「俳優」という言葉も浸透し始めたのです。西洋文化の影響を受けて、より正式で格式高い表現として使われるようになりました。
私の祖母に聞いた話では、昔は「役者」というと少し軽んじられるような印象があったそうですが、「俳優」と言うと品格があるように感じられたとのことでした。
使い分けのポイント
伝統芸能の場合
歌舞伎や能などの伝統芸能では、「役者」という言葉が好まれます。例えば:
- 「市川團十郎は偉大な歌舞伎役者だ」
- 「この能役者の演技は素晴らしい」
現代の映画・テレビの場合
映画やテレビドラマでは、「俳優」という言葉がよく使われます。例えば:
- 「この映画の主演俳優は演技が上手い」
- 「人気俳優が新しいドラマに出演する」
一般的な演技者を指す場合
役者に関しては、テレビドラマや映画、舞台などの他に能や歌舞伎などで演技をする人たちも含まれているので、より範囲が広いということが言えます。
そのため、演技をする人全般を指す時は「役者」を使うことが多いです。
実際の例文で理解する使い分け
役者を使った例文
- 「彼は舞台役者として20年のキャリアを積んでいる」
- 「この劇団の役者たちは皆、演技力が高い」
- 「役者としての表現力が素晴らしい」
- 「ベテラン役者の迫真の演技に感動した」
- 「役者冥利に尽きる瞬間だった」
俳優を使った例文
- 「映画俳優として数々の作品に出演している」
- 「この俳優は演技派として知られている」
- 「テレビドラマの主演俳優が発表された」
- 「若手俳優の成長が著しい」
- 「俳優業と歌手業を両立している」
業界内での使い分け
歌舞伎界での特別な使い分け
興味深いことに、正式には、「日本俳優協会」に加盟しているプロを「歌舞伎俳優」と言い、加盟していない人を「歌舞伎役者」と言います。このような細かい区別があることも、使い分けの複雑さを物語っています。
映画・テレビ業界での使い分け
1950年代から1960年代にかけて五社協定という取り決めがあり、映画会社と専属契約を結んだいわゆる映画俳優は、自社製作の映画以外への出演が制限されるなど、明確に活動範囲を区分されていた。
このような歴史的背景から、映画・テレビ業界では「俳優」という言葉が定着したのです。
現代における使い分けの実情
メディアでの使われ方
現代のメディアでは、どちらの言葉も使われていますが、少し傾向があります:
- 新聞や雑誌:「俳優」を使うことが多い
- 業界関係者:「役者」を使うことが多い
- 一般の人々:どちらも使うが、「俳優」の方が丁寧な印象
年代による違い
私の経験では、年配の方は「役者」を使うことが多く、若い世代は「俳優」を使う傾向があります。これは、それぞれの時代の文化的背景が影響しているのかもしれません。
あなたを奪ったその日から
— DAIGO (@Daigo19780408) June 30, 2025
最高の最終回でした
泣きました
それぞれが歩き出しました
玖村もあの後頑張ることでしょう
俳優の皆様、監督、スタッフさん、観て頂いた皆様、本当にありがとうございました。
※DAIGOは一切出演していませんが妻が頑張ったドラマでした#あなたを奪ったその日から pic.twitter.com/K7KTDJCVPI
類似する言葉との違い
役者・俳優・演者の違い
役者(やくしゃ)とは、俳優さんのこと。舞台やミュージカル、時代劇などで演技をする人を指します。
「演者」という言葉もありますが、これは演技だけでなく、歌手や芸人など、より広い意味での「演じる人」を指します。
芸能人との違い
俳優や役者は演技を専門とする人ですが、芸能人はより広い概念で、歌手、タレント、芸人なども含みます。
よくある質問
Q1: 同じ人について「役者」と「俳優」どちらを使えばいいの?
どちらを使っても間違いではありませんが、以下のような使い分けがおすすめです:
- 伝統芸能(歌舞伎、能など)の場合:「役者」
- 映画・テレビの場合:「俳優」
- 舞台全般の場合:どちらでも可
例:「木村拓哉は人気俳優だ」「市川海老蔵は歌舞伎役者だ」
Q2: 女性の場合はどう呼ぶの?
女性の場合は以下のような使い分けがあります:
- 役者:「女役者」または単に「役者」
- 俳優:「女優」または「俳優」
最近では性別に関係なく「俳優」を使うことも増えています。
Q3: 子役の場合はどう呼ぶの?
子役の場合は一般的に「子役俳優」または単に「子役」と呼ばれることが多いです。
「子役者」という言葉もありますが、あまり一般的ではありません。
Q4: 海外の演技者の場合はどう呼ぶの?
海外の演技者の場合は「俳優」を使うのが一般的です。
例:「ハリウッド俳優」「韓国俳優」
「海外役者」という表現はあまり使われません。
「役者」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ
「役者」と「俳優」の違いについて詳しく解説してきました。重要なポイントをまとめると:
役者は日本の伝統的な演劇文化と深く結びついた言葉で、歌舞伎や能などの伝統芸能、そして演技をする人全般を指す際に使われます。親しみやすく、業界内でよく使われる表現です。
俳優は明治時代に西洋文化の影響で広まった言葉で、映画やテレビドラマなどの現代的なメディアで活躍する演技者を指す際によく使われます。より格式高く、公式な場面で好まれる表現です。
現代では両者の意味はほぼ同じですが、文脈や対象によって使い分けることで、より適切で自然な表現ができるようになります。
普段の会話では、どちらを使っても問題ありませんが、この記事で紹介した使い分けのポイントを参考にしていただければ、より豊かな日本語表現ができるようになるでしょう。言葉の背景を知ることで、日本の文化や歴史への理解も深まりますね。