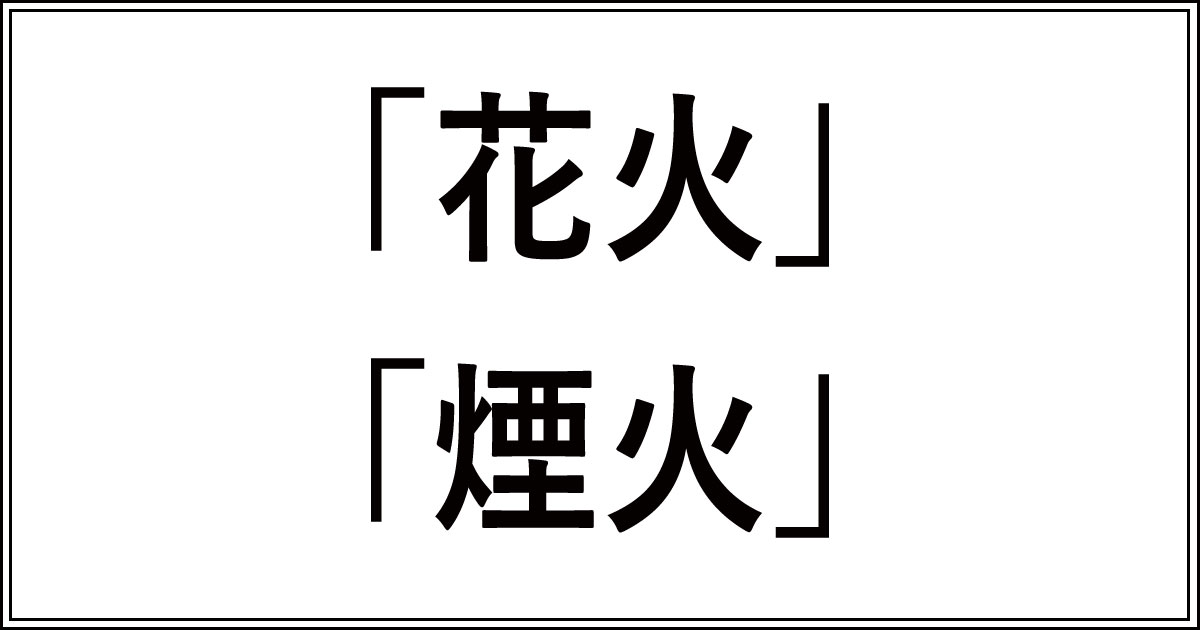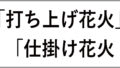夏の夜空を彩る美しい花火。でも実は、同じ花火でも「花火」と「煙火」という2つの表記があることをご存知ですか?どちらも読み方は同じ「はなび」ですが、実はちょっとした違いがあるんです。私も子どもの頃から花火大会を見に行くのが大好きで、最近では家族で手持ち花火を楽しんでいるのですが、この違いを知ってから花火を見る目が変わりました。今回は、似ているようで少し違う「花火」と「煙火」について、わかりやすく解説していきますね。
「花火」と「煙火」の基本的な意味
花火とは
「花火」は、私たちが普段よく使う言葉ですね。火薬類を燃焼・爆発させ、光(色)、音、そして煙を発生させるもので、現在では一般的な鑑賞に用いられるほか、合図や信号としても使われています。夏祭りで見る打ち上げ花火から、お家で楽しむ手持ち花火まで、すべて花火と呼びます。
煙火とは
一方、「煙火」は「はなび」や「えんか」と読みますが、実は花火よりも意味が広いんです。「煙火」には3つの意味があります。1つめは煙と火のこと、または炊事の煙のこと、2つめはのろしのこと、3つめは花火のことです。つまり、煙火は花火の意味も含みつつ、それ以外の煙や火も表す言葉なんですね。
法律上での違い:公的用語としての「煙火」
ここが一番重要なポイントです!花火は、火薬取締法という法律では「煙火」と呼ばれており、法律や公的な場面では必ず「煙火」という表記が使われます。花火は公的用語としては「煙火(えんか)」といわれ、その製造、貯蔵、販売等は火薬類取締法によって規制されているのです。
私が花火大会のパンフレットをじっくり見た時に気がついたのですが、主催者の挨拶や注意事項には「煙火」という表記がよく使われているんです。これは法律に関わる内容だからなんですね。
花火業界でも「煙火」が一般的
実は、花火を作る会社でも「煙火」の方がよく使われています。花火会社はほとんどこの名称を使っています。**煙火店、**煙火、**煙火工場、**煙火製作所などです。意外に**花火という会社は、珍しいのです。プロの世界では「煙火」の方が一般的だったんですね。
花火と煙火の分類について
煙火の分類
煙火を大きく分類すると”玩具花火”、”煙火”の2つになります。さらに煙火を分類すると、①打上煙火、②仕掛煙火、③その他の煙火に分けられます。
法律上では、私たちが普段楽しむ手持ち花火は「がん具用煙火」と呼ばれ、花火大会で見る大きな花火は「がん具用煙火以外の煙火」という分類になります。ちょっと堅い表現ですが、要するに一般向けか業務用かの違いですね。
打ち上げ花火の種類
打ち上げ花火にも様々な種類があります。代表的なものは、菊のように球形に開く「割物」と、花火玉が上空で二つに開いて中から星が放出される「ポカ物」があります。どちらも美しいですが、それぞれ全く違う仕組みで作られているんです。
想い弾ける線香花火 pic.twitter.com/pTQ4Fr3B6L
— ひらゆい (@yuiphoto2) July 14, 2025
実際の使い分け方と例文
日常会話では「花火」
普段の会話では「花火」を使うのが自然です。
例文:
- 「今度の土曜日、花火大会に行こうよ」
- 「子どもたちと花火をして遊んだ」
- 「夏といえば花火だよね」
公的・法的な場面では「煙火」
法律や規則、業界関係者との会話では「煙火」を使います。
例文:
- 「煙火の製造には火薬類取締法の許可が必要です」
- 「煙火打上げ許可申請書を提出してください」
- 「この地域では煙火の使用が禁止されています」
文学的・伝統的な表現では「煙火」
詩や俳句、伝統的な文章では「煙火」が使われることもあります。
例文:
- 「夜空に咲く煙火の美しさに心を奪われた」
- 「祭りの煙火が夏の終わりを告げている」
私の体験談:花火大会での発見
去年の夏、地元の花火大会に家族で出かけた時のことです。会場で配られたプログラムを見ていると、「煙火協賛企業」「煙火保安距離」という表記があることに気がつきました。「あれ?花火大会なのに、なぜ煙火って書いてあるんだろう?」と疑問に思って調べてみたのが、この違いを知るきっかけでした。
プログラムの最後の方には、しっかりと「火薬類取締法に基づく煙火の取り扱いについて」という注意書きもありました。安全に花火大会を開催するためには、法律に従って適切に管理する必要があるんですね。
のろしとしての煙火
意外かもしれませんが、「煙火」には「のろし」の意味もあるんです。昔の人は、遠くの人に合図を送るために高い場所で火を焚いて煙を上げていました。これも煙火の一種なんですね。現代でも、山での遭難信号や船舶の緊急時に使われる発煙筒なども、広い意味では煙火に含まれます。
花火の歴史と言葉の変遷
花火の歴史は古く、もともとは中国から伝わったとされています。日本では江戸時代から庶民の間で親しまれるようになりました。当時は「花火」という表記が一般的でしたが、明治時代に入って法律が整備されると、正式な用語として「煙火」が使われるようになったんです。
私の住んでいる地域にも老舗の煙火店があるのですが、創業当時からの看板には確かに「煙火」と書かれています。伝統を大切にしながら、現代まで技術を受け継いでいるんですね。
よくある質問
Q1. 「花火」と「煙火」はどちらを使えばいいの?
普段の会話や文章では「花火」を使うのが一般的です。ただし、法律関係の書類や業務で関わる場合は「煙火」を使いましょう。迷った時は、相手や場面に合わせて選ぶといいですね。私も友達との会話では「花火」、子どもの学校の行事で安全について説明する時は「煙火」を使うようにしています。
Q2. 花火大会のプログラムに「煙火」と書いてあるのはなぜ?
花火大会は火薬を扱う危険な行事でもあるため、法律に基づいた許可や安全対策が必要です。そのため、公式な書類やプログラムでは法律用語である「煙火」が使われることが多いんです。安全第一で開催されているからこそ、私たちは安心して花火を楽しめるんですね。
Q3. 手持ち花火も「煙火」と呼ぶの?
はい、法律上は手持ち花火も「がん具用煙火」という正式名称があります。ただし、普段の生活では「花火」と呼ぶ方が自然です。お店でも「花火コーナー」として売られていることがほとんどですよね。私も子どもたちと「今日は花火をしよう」と言って楽しんでいます。
Q4. なぜ花火業界では「煙火」を使うの?
花火を製造・販売する業者は火薬類取締法の規制を受けるため、法律用語に合わせて「煙火」を使うことが多いんです。また、伝統的にこの業界では「煙火」という言葉が定着しているという歴史的な背景もあります。プロの世界では正確な用語を使うことが大切なんですね。
「花火」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ
「花火」と「煙火」の違いをまとめると:
花火は私たちが普段使う一般的な言葉で、夏の楽しいイベントや家族の思い出作りに欠かせないもの。友達や家族との会話では「花火」を使うのが自然です。
煙火は法律用語としての正式名称で、花火業界や公的な場面で使われる言葉。また、のろしや炊事の煙など、より広い意味も含んでいます。
どちらも同じものを指していますが、使う場面や相手によって使い分けることで、より適切なコミュニケーションができますね。私も最初は違いがよくわからなかったのですが、調べてみると奥が深くて面白い発見がたくさんありました。
次に花火大会に行く時や、子どもたちと手持ち花火を楽しむ時は、この豆知識を思い出してみてください。きっと花火がより特別なものに感じられるはずです。夏の夜空を彩る美しい光に、また一つ新しい視点が加わりますね。