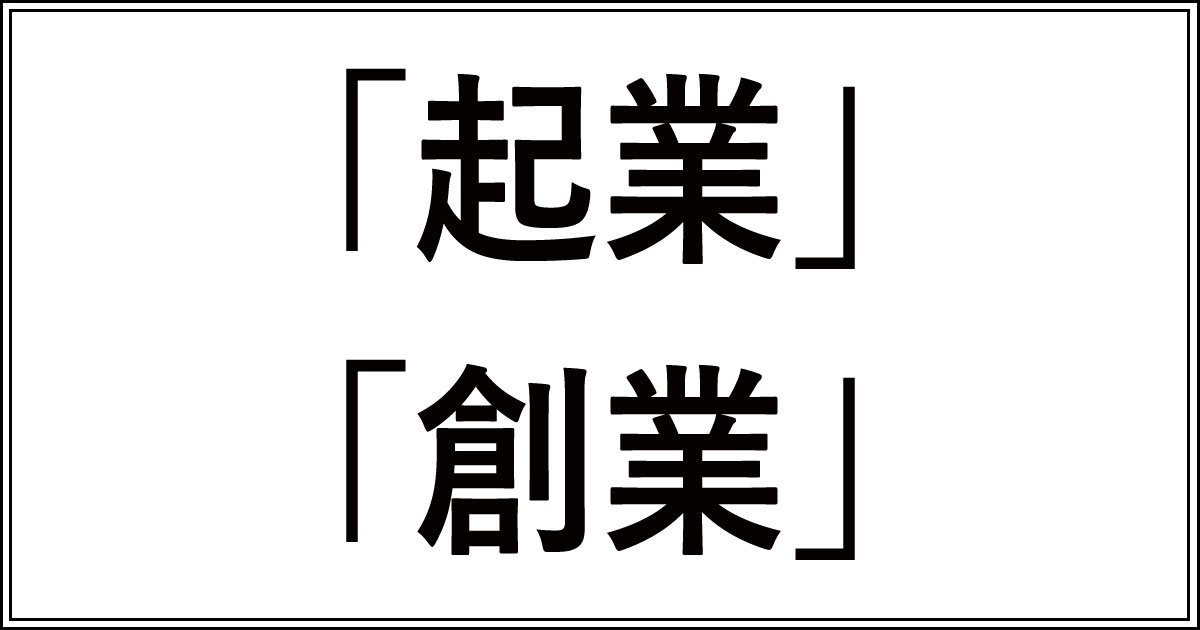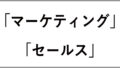「起業をしようと考えています」「創業から5年が経ちました」という言葉を聞いたことがありませんか?どちらも「新しく事業を始める」という意味で使われることが多いのですが、実は微妙な違いがあるんです。
私自身、子育てをしながら在宅でできる仕事を始めようと思った時に、この2つの言葉の使い分けについて疑問に思いました。友人に「来年創業する予定なの」と話した時に「それって起業じゃない?」と指摘されて、初めてこの2つの言葉の違いを知ったんです。
同じような疑問を持つ方のために、今回は「起業」と「創業」の違いを分かりやすく説明します。正しく使い分けられるようになると、ビジネスの場面でも恥をかかずに済みますよ。
関連記事
「ベンチャー企業」と「スタートアップ」の違いを例文付きで解説!
「創業」と「設立」の違い!意味や使い分け
「起業」の意味と特徴を詳しく解説
起業とは、「新しく事業を起こすこと」という意味です。起業は未来のことを示しますので、これから事業を始めようとする時によく使われます。
起業の特徴として、以下のようなポイントがあります:
時間軸:未来や近い将来の出来事を指すことが多い ニュアンス:チャレンジ精神や新しいことに挑戦するという意味合いが強い 使用場面:ベンチャー企業やスタートアップなど革新的な事業を始める場合
例えば、新しいアプリを作って会社を立ち上げる場合や、これまでにないサービスを提供する事業を始める場合などは「起業」という言葉がぴったりです。
「創業」の意味と特徴を詳しく解説
創業とは、「事業を始めること」「会社や店を新しく興すこと」という意味です。創業は主に過去のことを示すため、すでに事業を始めた後によく使われる言葉です。
創業の特徴として、以下のようなポイントがあります:
時間軸:過去の出来事や歴史を語る時に使われることが多い ニュアンス:伝統的で格式のあるイメージ 使用場面:会社の歴史や沿革を説明する時、記念日や節目の時
老舗の呉服店が「創業100年」と看板に掲げたり、会社のホームページで「昭和30年創業」と書いたりするのを見たことがあると思います。これらはすべて、過去に事業を始めたという意味で「創業」を使っているのです。
時間軸で見る「起業」と「創業」の使い分け方
この2つの言葉の最も大きな違いは、使われる時間軸です。簡単に言うと、未来のことを話す時は「起業」、過去のことを話す時は「創業」を使うのが自然です。
未来を指す場合(起業を使う)
- 「来年起業する予定です」
- 「今度起業しようと思っています」
- 「起業を考えている友人がいます」
- 「起業に向けて準備を進めています」
過去を指す場合(創業を使う)
- 「3年前に創業しました」
- 「創業から10年が経ちました」
- 「創業当時は大変でした」
- 「創業者の想いを大切にしています」
私の経験でも、友人と話す時に「来年創業する予定」と言ったら違和感を持たれたのは、この時間軸の使い分けができていなかったからなんですね。
セコくていいんです。
— ウダガワ | 売れる会社を創る男 (@vp_udagawa) July 21, 2025
僕たち凡人起業家は。
カッコよくなくていい。
志なんていらない。
勝てば官軍なのです。
実際の使用例と間違いやすいパターン
正しい使い分けを理解するために、具体的な例文を見てみましょう。
正しい使用例
起業の正しい使用例:
- 「大学卒業後、すぐに起業したいと考えています」
- 「IT関連の事業で起業を目指しています」
- 「起業セミナーに参加して勉強中です」
- 「起業家として成功したいと思います」
創業の正しい使用例:
- 「弊社は昭和50年の創業です」
- 「創業以来、お客様第一を心がけています」
- 「創業記念日にパーティーを開催します」
- 「創業者の理念を受け継いでいます」
間違いやすいパターン
❌ 間違った使い方:
- 「来年創業する予定です」→「来年起業する予定です」
- 「起業から5年が経ちました」→「創業から5年が経ちました」
- 「創業を目指しています」→「起業を目指しています」
このような間違いは意外と多く、ビジネス文書や会話の中でもよく見かけます。正しく使い分けることで、相手に与える印象も変わってきます。
ビジネスシーンでの適切な使い分け方法
ビジネスの場面では、相手や状況に応じて適切な言葉を選ぶことが大切です。
起業を使う場面
- 事業計画を説明する時
- 投資家にプレゼンテーションする時
- 新しいビジネスアイデアを話し合う時
- 将来の目標について語る時
「私たちは来年の4月に起業を予定しており、革新的なサービスを提供していく予定です」といったように、未来への意気込みを表現する時に効果的です。
創業を使う場面
- 会社の沿革を説明する時
- 創立記念日のスピーチをする時
- 企業理念について語る時
- 会社の歴史や伝統を紹介する時
「弊社は昭和40年の創業以来、地域に根差したサービスを提供してまいりました」といったように、会社の歴史や信頼性をアピールする時に使います。
関連する類似語との違いも理解しよう
起業と創業以外にも、似たような意味で使われる言葉があります。これらも併せて理解しておくと、より正確な使い分けができるようになります。
開業
「開業」は、主に個人事業主が事業を始める時や、店舗を開く時に使われます。「歯科医院を開業する」「美容室を開業する」といった具合です。法人設立よりも、個人レベルでの事業開始というニュアンスが強いです。
設立
「設立」は、法人格を取得して会社を作ることを指します。「株式会社を設立する」「有限会社を設立する」といったように、法的な手続きを含む会社の設立に使われます。
創設
「創設」は、組織や団体を新しく作ることを意味します。「委員会を創設する」「基金を創設する」といったように、営利企業以外の組織にも使われることが多いです。
吉野家 ル・シーニュ府中店@府中
— ナッキー®︎ (@kiyonakadai) July 16, 2025
牛玉スタミナまぜそば(半熟)+納豆
新しくオープンした吉野家で創業125年目で初めての中華麺メニューを食べてみました。満席で盛況❗️ pic.twitter.com/HfasyLiFFa
私の体験談:起業と創業を使い分けて学んだこと
実は私、この記事を書くきっかけになった体験があります。子育てをしながら何か新しいことを始めたいと思い、友人たちと話していた時のことでした。
「来年、家事代行サービスで創業しようと思っているんだ」と話したところ、起業経験のある友人から「それは起業じゃない?創業って言うと、もう始めているみたいに聞こえるよ」と指摘されました。
最初は「同じような意味なのに、なぜそんなに細かく言うの?」と思いましたが、調べてみると確かに使い分けがあることが分かりました。その後、正しく「起業を予定している」と言うようになってから、相手との会話もスムーズになったような気がします。
特に、銀行で事業資金の相談をする時には、「来年4月に起業予定で、現在準備を進めています」と説明することで、担当者の方にも計画の段階であることがきちんと伝わりました。言葉の使い分けって、思っている以上に大切なんだなと実感した出来事でした。
よくある質問
Q1:「起業予定」と「創業予定」のどちらが正しいですか?
未来のことを表す場合は「起業予定」が正しい使い方です。創業は、事業を始めた後に用いる言葉なので、「創業予定」という表現は不自然に感じられる可能性があります。事業を始める前の段階では「起業予定」を使うようにしましょう。
Q2:会社のホームページには「起業」と「創業」のどちらを使うべきですか?
会社の沿革や歴史を紹介するページでは「創業」を使うのが一般的です。「創業1985年」「創業から40年」といった表現が適切です。一方、代表者のメッセージで将来のビジョンを語る場合は「起業」を使うことがあります。
Q3:起業家と創業者の違いはありますか?
「起業家」は事業を起こす人全般を指し、現在進行形で事業を展開している人を表します。「創業者」は会社や事業を最初に立ち上げた人を指し、歴史的な文脈で使われることが多いです。現在活動している人には「起業家」、会社の歴史を語る時には「創業者」を使うのが適切です。
Q4:個人事業主の場合も「起業」「創業」を使えますか?
個人事業主の場合も使えますが、「開業」という言葉を使うことの方が多いです。例えば、「来年、個人事業主として起業予定です」「3年前に創業した個人事業です」といった使い方も可能ですが、「来年開業予定です」「3年前に開業しました」の方が一般的です。
「ビジネス」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ
「起業」と「創業」の違いをまとめると、以下のようになります:
起業は未来や計画段階の事業開始を指し、チャレンジ精神や革新的なニュアンスを含みます。「来年起業予定です」「起業を目指しています」といったように、これから事業を始める時に使います。
創業は過去の事業開始や会社の歴史を指し、格式があり伝統的なニュアンスを含みます。「創業10年」「創業者の理念」といったように、すでに事業が始まっている状態や歴史を語る時に使います。
正しく使い分けることで、相手に与える印象も変わり、ビジネスシーンでもより適切なコミュニケーションが取れるようになります。私の体験談でもお話ししたように、最初は小さな違いに思えても、正確に使い分けることで会話がスムーズになり、相手に伝わりやすくなります。
これから事業を始めようと考えている方も、すでに事業を営んでいる方も、場面に応じて「起業」と「創業」を使い分けて、より効果的なコミュニケーションを心がけてくださいね。