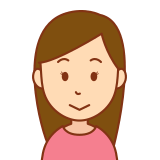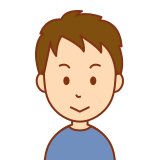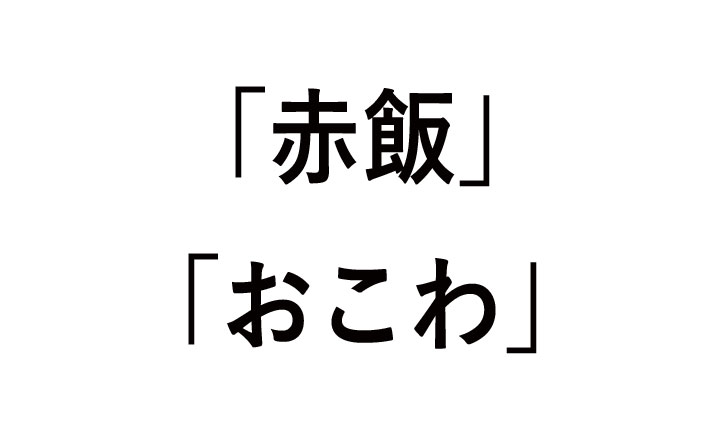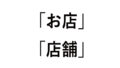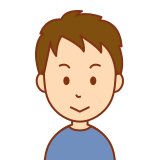
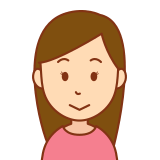
赤飯とおこわは日本の伝統的な米料理です。違いや由来について説明します。
赤飯とおこわの違い
結論から言うと、現代では赤飯とおこわに明確な違いはありません。
おこわはもち米を炊いたり蒸したりする米飯の総称で、小豆ともち米を蒸して作る赤飯はおこわの種類のひとつです。
明治時代頃までは、赤飯とおこわは別物だと考えられていましたが、時代が進むにつれてその区別があいまいになりました。
赤飯とは
赤飯は、もち米を使って調理されることが一般的で、赤い色合いが特徴です。この色は、主に赤飯に使われるあかめ、ぜんざいなどの赤い豆や調味料から来ています。甘くて少し塩気のある味付けがされることもあります。お祝いごとや特別な日に供されることが多いです。
赤飯の由来
一説によれば、赤飯は古代中国の儀式料理に由来するとされています。中国の儀式では、お米に鮮やかな色素を加えて祭祀や特別な行事で供されたことがあり、これが赤飯の起源とされています。
また、日本における赤い色の象徴として、神聖なものや幸運を象徴するという考え方もあります。そのため、特別な日や祝いの席で赤い色を持つ赤飯が用いられるようになったという説もあります。
赤い豆を加えることで食べる人に幸運や邪気を払う力があると信じられていたことも赤飯の起源と関連付けられています。
おこわとは
おこわは、もち米蒸して作った料理を指します。
地域や家庭によって作り方や味付けが異なり、塩味や甘味が強いバリエーションがあります。
おこわの由来
おこわは、「強飯(こわめし/こわいい)」という言葉が一般的に使われるようになったことから生まれた言葉です。
もち米を蒸したごはんは普通のごはんよりかたいため、こわい(堅い)飯と呼ばれたのがおこわの由来です。
おこわの原型は、古代から続く米飯の一種であり、祭りや行事、特別な日に供されてきたと考えられています。地域によっても異なる呼び名や作り方があり、それぞれの文化や風習に合わせて発展してきた歴史があります。