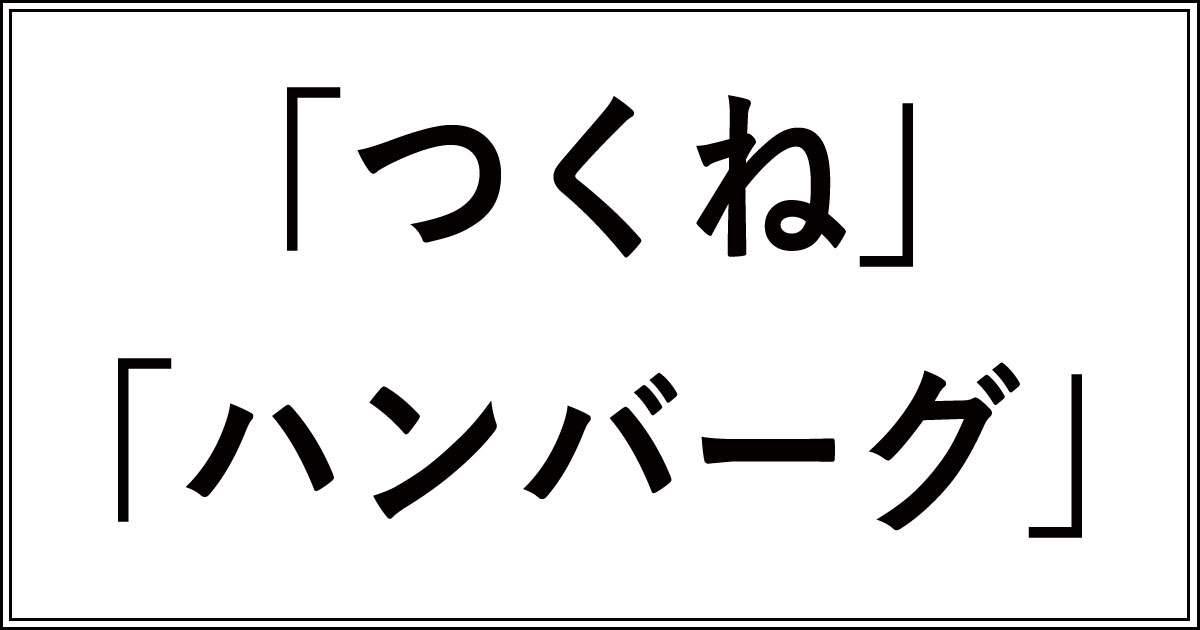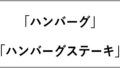「つくねって、ハンバーグと何が違うの?」と疑問に思ったことはありませんか?どちらも挽肉を使って作る料理で、見た目も似ているため、混同してしまいがちです。実は、この2つの料理にはしっかりとした違いがあるんです。
料理好きの私も、以前は「つくね=小さなハンバーグ」程度の認識でしたが、実際に作り比べてみると、材料や調理法、食感まで全く異なることがわかりました。今回は、つくねとハンバーグの違いを詳しく解説し、正しい理解を深めていただけるよう例文とともにお伝えします。
これを読めば、もう混同することなく、それぞれの料理の特徴を理解して美味しく作れるようになりますよ。
関連記事
「生つくね」と「つくね」の違い!料理方法や味や食感
「鶏団子」と「つくね」の違い!作り方や栄養
「つくね」と「ハンバーグ」の違い!特徴や味や食感
「メンチカツ」と「ハンバーグ」の違い!材料や調理法
「ミートボール」と「ハンバーグ」の違い!材料やアレンジレシピ
「パティ」と「ハンバーグ」の違い!材料や使い分けを解説!
つくねとハンバーグの基本的な違い
使用する肉の違い
つくねとハンバーグの最も大きな違いは、使用する肉の種類です。
つくねは、主に鶏肉を使用します。鶏のひき肉が一般的で、時には魚のすり身を使うこともあります。「今日は鶏のつくねを作ろう」「いわしのつくねが美味しい」といった使い方をします。
一方、ハンバーグは牛肉が基本です。牛肉100%のもの、または牛肉と豚肉を混ぜた合いびき肉を使用します。「牛肉のハンバーグステーキ」「合いびきハンバーグ」といった表現が一般的です。
調理法の違い
つくねは手でこねて丸める調理法が特徴的です。「つくね」の語源は「手でこねる」という意味の「捏ねる(つくねる)」から来ています。基本的に丸い形に成形し、串に刺して焼くことが多いです。
ハンバーグは、材料を混ぜ合わせた後、平たい楕円形に成形します。フライパンで焼くのが一般的で、ステーキのように皿に盛り付けて提供されます。
つくねの特徴と例文での表現
つくねの基本的な特徴
つくねは和食の代表的な料理で、以下の特徴があります。
材料面の特徴
- 鶏ひき肉が主原料
- 卵、片栗粉、調味料を加えて粘りを出す
- 長ねぎやしょうが、しそなどの薬味を加えることが多い
調理面の特徴
- 手でこねて丸める成形方法
- 串に刺して焼く場合が多い
- 照り焼きのタレで味付けすることが一般的
私が実際につくねを作る際は、鶏ひき肉に卵と片栗粉を加えて、手でよくこねることを心がけています。この工程で粘りが出て、つくね特有のもちもちした食感が生まれるんです。
つくねの例文での表現
- 「今夜は焼き鳥屋さん風のつくねを作ります」
- 「お弁当に入れるつくねは、少し小さめに作りましょう」
- 「鍋料理にはつくねを加えると美味しくなります」
- 「つくねには甘辛いタレがよく合います」
ハンバーグの特徴と例文での表現
ハンバーグの基本的な特徴
ハンバーグは洋食の代表的な料理で、以下の特徴があります。
材料面の特徴
- 牛肉または合いびき肉が主原料
- パン粉、牛乳、卵を加えてふんわり感を出す
- 玉ねぎを炒めて甘みを加える
調理面の特徴
- 平たい楕円形に成形する
- フライパンで焼く調理法
- デミグラスソースやケチャップソースで味付け
我が家でハンバーグを作る時は、玉ねぎを飴色になるまで炒めることにこだわっています。この一手間で、ハンバーグの甘みと旨みが格段にアップするんです。
ハンバーグの例文での表現
- 「週末の夜はハンバーグステーキにしましょう」
- 「お子様にはチーズハンバーグが人気です」
- 「ハンバーグにはデミグラスソースをかけて召し上がれ」
- 「煮込みハンバーグは寒い日にぴったりです」
おいしいつくね。 pic.twitter.com/wYkwPU6PA2
— ねむり (@NyF19sjYae84392) July 5, 2025
味と食感の違い
つくねの味と食感
つくねは、鶏肉特有のあっさりとした味わいが特徴です。手でこねることで生まれる弾力のある食感と、照り焼きのタレの甘辛い味付けが魅力的です。
実際に食べてみると、つくねはもちもちとした食感で、噛むほどに旨みが広がります。特に、軟骨を混ぜたつくねは、プチプチとした食感のアクセントが楽しめます。
ハンバーグの味と食感
ハンバーグは、牛肉のコクと旨みが凝縮された濃厚な味わいが特徴です。パン粉と牛乳を加えることで、ふんわりとジューシーな食感に仕上がります。
我が家では、ハンバーグを作る時に中央を少しくぼませて焼くことで、中まで均一に火が通り、ジューシーな仕上がりになります。この小技は、母から教わった大切なコツです。
料理での表現の違い
つくねを表現する場面
つくねは和食の料理に幅広く活用できます。
焼き鳥 串に刺して炭火で焼く、最も一般的な調理法です。「今日は焼き鳥屋さんでつくねを注文しよう」
鍋料理 水炊きやちゃんこ鍋に加えると、出汁が美味しくなります。「鍋にはつくねを必ず入れます」
お弁当のおかず 小さめに作れば、お弁当にぴったりです。「お弁当にはつくねの照り焼きを入れました」
ハンバーグを表現する場面
ハンバーグは洋食のメイン料理として活用されます。
ハンバーグステーキ 最も一般的な調理法で、ソースをかけて提供します。「今夜のメインはハンバーグステーキです」
煮込みハンバーグ トマトソースやデミグラスソースで煮込んだ料理です。「煮込みハンバーグは子供たちに大人気です」
ハンバーガー パンに挟んでハンバーガーとして楽しめます。「手作りハンバーガーのパティを作りました」
作り方の違いを詳しく解説
つくねの作り方のポイント
つくね作りで重要なのは、材料をしっかりとこねることです。
材料の準備
- 鶏ひき肉:300g
- 卵:1個
- 片栗粉:大さじ1
- 長ねぎ:1/2本(みじん切り)
- しょうが:1片(すりおろし)
- 塩、こしょう:少々
作り方のコツ
- 材料をボウルに入れて、手で粘りが出るまでよくこねる
- 手を水で濡らして、丸く成形する
- 串に刺して焼く、または丸いまま焼く
- 照り焼きのタレを絡めて完成
私が実際に作る時は、材料をこねる際に手を少し湿らせることで、肉が手にくっつかず、きれいに成形できます。
我が家のハンバーグはエノキと豆腐がたっぷり pic.twitter.com/tgCICEq7Gw
— かなめ丼 (@kaname_OAl7) July 8, 2025
ハンバーグの作り方のポイント
ハンバーグ作りで重要なのは、材料の配合と成形の仕方です。
材料の準備
- 合いびき肉:300g
- 玉ねぎ:1/2個(みじん切り)
- パン粉:1/2カップ
- 牛乳:大さじ3
- 卵:1個
- 塩、こしょう:少々
作り方のコツ
- 玉ねぎを炒めて冷ましておく
- パン粉を牛乳に浸しておく
- 材料を混ぜ合わせて、平たい楕円形に成形
- 中央を少しくぼませる
- フライパンで両面を焼く
ハンバーグを作る時は、成形後に冷蔵庫で30分程度休ませることで、形が崩れにくくなります。これは、料理教室で教わったテクニックです。
栄養面での違い
つくねの栄養特徴
つくねは鶏肉が主原料なので、比較的低カロリーで高タンパクな料理です。
主な栄養成分
- タンパク質が豊富
- 脂質が比較的少ない
- ビタミンB群が含まれる
- コラーゲンが豊富(軟骨入りの場合)
ダイエット中の方や、あっさりした料理を好む方には、つくねがおすすめです。
ハンバーグの栄養特徴
ハンバーグは牛肉が主原料なので、鉄分やビタミンB12が豊富です。
主な栄養成分
- 鉄分が豊富
- ビタミンB12が含まれる
- 亜鉛が豊富
- タンパク質が豊富
成長期の子供や、貧血気味の方には、ハンバーグの栄養価が魅力的です。
地域による違いと特色
各地のつくね文化
つくねは日本全国で親しまれている料理ですが、地域によって特色があります。
関西風つくね 関西では、つくねに軟骨を入れることが多く、食感のアクセントを楽しみます。「関西のつくねは軟骨入りが定番です」
九州風つくね 九州では、つくねに明太子を加えたり、柚子胡椒で味付けしたりする場合があります。
各地のハンバーグ文化
ハンバーグも地域によって特色があります。
洋食屋のハンバーグ 老舗の洋食屋では、デミグラスソースにこだわったハンバーグが人気です。「老舗洋食屋の手作りハンバーグは絶品です」
ファミリーレストランのハンバーグ ファミリーレストランでは、チーズハンバーグや和風ハンバーグなど、アレンジメニューが豊富です。
保存方法と日持ちの違い
つくねの保存方法
つくねは手作りした場合、以下の方法で保存できます。
冷蔵保存
- 調理済みのつくね:2-3日
- 生のつくね:当日中に調理
冷凍保存
- 調理済みのつくね:1ヶ月程度
- 生のつくね:2週間程度
我が家では、つくねを多めに作って冷凍保存しています。お弁当に入れる時は、前日に冷蔵庫で自然解凍してから使います。
ハンバーグの保存方法
ハンバーグも同様に保存できます。
冷蔵保存
- 調理済みのハンバーグ:2-3日
- 生のハンバーグ:当日中に調理
冷凍保存
- 調理済みのハンバーグ:1ヶ月程度
- 生のハンバーグ:2週間程度
ハンバーグは、成形後に冷凍保存することで、忙しい日でも手軽に調理できます。
よくある質問
Q1. つくねとハンバーグ、どちらが作りやすいですか?
つくねの方が作りやすいと言えます。材料が少なく、手でこねて丸めるだけなので、初心者でも失敗しにくいです。ハンバーグは玉ねぎを炒めたり、形を整えたりする工程が多く、少し手間がかかります。
実際に私が料理を始めた頃は、つくねから挑戦しました。シンプルな材料と工程で、美味しく作れたので自信につながりました。
Q2. つくねとハンバーグ、子供にはどちらが人気ですか?
一般的には、ハンバーグの方が子供に人気です。洋食として馴染みがあり、ケチャップやチーズと合わせやすいためです。つくねは和食の味付けなので、子供によって好みが分かれます。
我が家でも、子供たちはハンバーグの方を好む傾向があります。ただし、つくねも甘辛いタレで味付けすると、子供たちに喜ばれます。
Q3. つくねとハンバーグ、どちらがヘルシーですか?
つくねの方がヘルシーと言えます。鶏肉は牛肉に比べて脂質が少なく、カロリーも控えめです。また、つくねは余分な調味料を使わずに、素材の味を活かした調理法が多いです。
ダイエット中の方や、あっさりした料理を好む方には、つくねがおすすめです。
Q4. つくねとハンバーグ、どちらが冷凍保存に向いていますか?
どちらも冷凍保存に向いていますが、つくねの方が解凍後の食感が保たれやすいです。ハンバーグは冷凍すると水分が出やすく、解凍後にパサつく場合があります。
冷凍保存する場合は、調理済みのものを急速冷凍し、解凍時は冷蔵庫でゆっくり解凍することがポイントです。
Q5. つくねとハンバーグ、どちらが栄養価が高いですか?
栄養価は材料によって異なりますが、ハンバーグの方が鉄分やビタミンB12などのミネラルが豊富です。つくねは高タンパクで低脂質なので、目的に応じて選ぶことが大切です。
成長期の子供には鉄分豊富なハンバーグ、ダイエット中の方には低カロリーなつくねがおすすめです。
「ハンバーグ」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ
つくねとハンバーグの違いをまとめると、以下のようになります。
つくね
- 主に鶏肉を使用
- 手でこねて丸く成形
- 和食の調味料で味付け
- もちもちした食感
- 比較的低カロリー
ハンバーグ
- 牛肉または合いびき肉を使用
- 平たい楕円形に成形
- 洋食のソースで味付け
- ふんわりジューシーな食感
- 鉄分やビタミンB12が豊富
どちらも美味しい料理ですが、材料、調理法、味付けに明確な違いがあります。今回の解説を参考に、それぞれの特徴を活かした料理を作ってみてください。きっと、より美味しく、そして楽しい料理時間になるはずです。