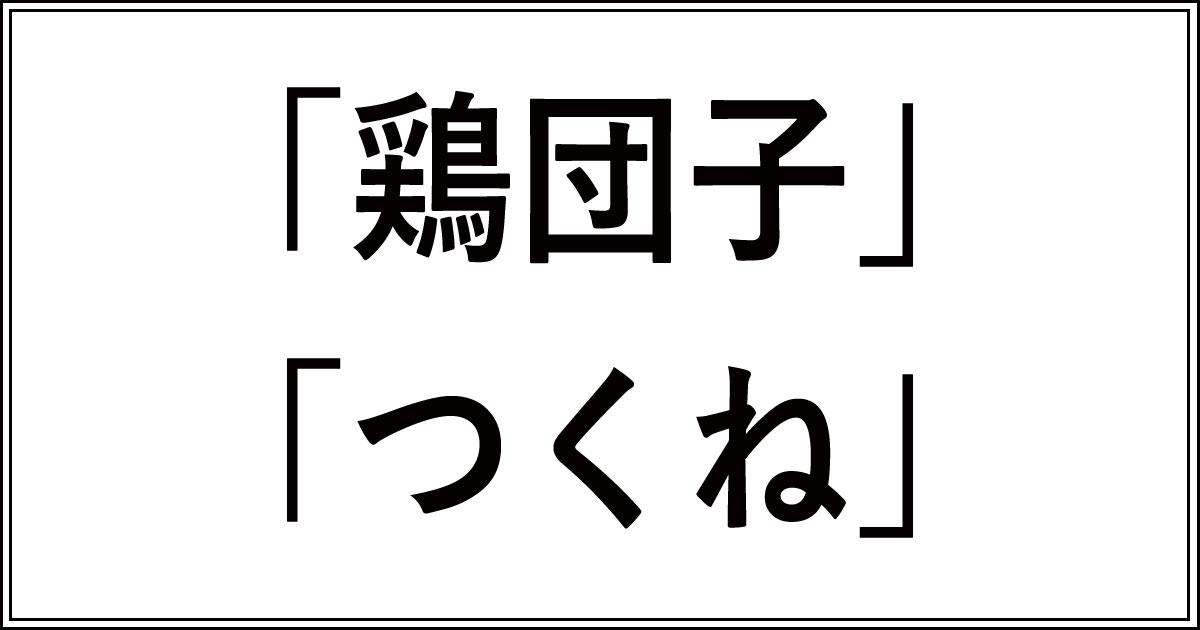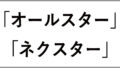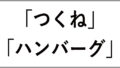「鶏団子」と「つくね」の違いについて説明できますか?実は多くの人が混同しているこの2つの言葉。日常会話でも、料理を作る時でも、正しく使い分けられていない場面をよく目にします。
今回は、「鶏団子」と「つくね」の違いを、具体的な例文を交えながら分かりやすく解説します。この記事を読めば、もう迷うことはありません!
関連記事
「つくね」と「ハンバーグ」の違い!特徴や味や食感
「生つくね」と「つくね」の違い!料理方法や味や食感
鶏団子とつくねの基本的な違い
まず最初に、鶏団子とつくねの基本的な違いを説明しましょう。
鶏団子とは、鶏ひき肉を丸めて作った団子状の料理全般を指します。形状に注目した呼び方で、調理方法は問いません。
つくねとは、鶏ひき肉などを「捏ね(こね)」て作る料理を指します。調理方法に注目した呼び方で、実は形状は関係ありません。
つまり、鶏団子は「見た目・形」に注目した名前で、つくねは「作り方・調理法」に注目した名前なのです。
語源から見る違い
鶏団子の語源
「鶏団子」の「団子」は、丸い形状を表す言葉です。つまり、鶏ひき肉を丸めて作った料理だから「鶏団子」と呼ばれるようになりました。
つくねの語源
「つくね」は漢字で「捏ね」と書き、「こねて作る料理を指し、食材は魚肉でもかまわない」とされています。手でこねて作る調理法に由来した名前なのです。
使い分けのポイント
形状に注目する場合:鶏団子
鶏団子は丸い形状に注目した呼び方です。以下のような場面で使います:
- スープに入れる丸い鶏肉の塊
- 鍋料理の具材として丸めたもの
- おでんの具材として丸く成形したもの
例文:
- 「今日の夕飯は鶏団子鍋にしよう」
- 「おでんに鶏団子を入れました」
- 「スープに鶏団子を浮かべて栄養満点」
調理法に注目する場合:つくね
つくねは調理方法に注目した呼び方です。以下のような場面で使います:
- 焼き鳥屋さんのメニュー
- 手でこねて作る料理
- 串に刺して焼く場合
例文:
- 「焼き鳥屋でつくねを注文した」
- 「手作りつくねを串に刺して焼きました」
- 「つくねのタレが美味しい」
実際の使い分けの例
私の実体験を交えて、具体的な使い分けの例を紹介します。
我が家での使い分け
我が家では、鍋料理やスープを作る時は「鶏団子」と呼んでいます。丸い形状が特徴的だからです。一方、バーベキューや焼き鳥風に調理する時は「つくね」と呼んでいます。
先日、子どもが「今日のご飯は何?」と聞いてきた時、「鶏団子鍋だよ」と答えました。すると子どもは「つくね鍋じゃないの?」と質問してきました。この時、「形が丸いから鶏団子、手でこねて作るからつくねっていうんだよ」と説明すると、子どもも納得してくれました。
料理本での使い分け
料理本やレシピサイトを見ると、この使い分けがよく分かります:
- 「鶏団子鍋」「鶏団子スープ」→ 丸い形状の料理
- 「つくね焼き」「つくね串」→ 調理方法に注目した料理
鶏団子あげるからお酒をおくれ pic.twitter.com/RMthfzhwTD
— 仁(8028) (@jinjin878) June 17, 2025
地域による違い
実は、地域によって呼び方が異なることもあります。
関東地方では、おでんの具材として「鶏団子」と呼ぶことが多いです。 関西地方では、同じものを「つくね」と呼ぶ傾向があります。
これは、関東では形状に注目する傾向があり、関西では調理方法に注目する傾向があるからかもしれません。
つくねと混同しやすい他の料理
つみれとの違い
つくねと混同しやすい料理に「つみれ」があります。
つみれは、魚のすり身を手で摘んで鍋に入れる調理法から生まれた名前です。主に魚を使い、手で摘んで成形します。
つくねは、主に鶏肉を使い、手でこねて成形します。
肉団子との違い
肉団子は、様々な肉を使って作る団子状の料理全般を指します。鶏肉だけでなく、豚肉や牛肉も使います。
鶏団子は、鶏肉のみを使った団子状の料理を指します。
栄養面での違い
鶏団子もつくねも、基本的には同じ鶏ひき肉を使って作るため、栄養面では大きな違いはありません。
どちらも良質なタンパク質を含み、比較的低脂質でヘルシーな料理です。調理方法によって、多少のカロリーの違いはありますが、栄養価は同じと考えて問題ありません。
作り方の違い
鶏団子の作り方
- 鶏ひき肉に調味料を加えて混ぜる
- 手で丸く成形する
- 茹でる・煮る・蒸すなど、水分を使って調理する
つくねの作り方
- 鶏ひき肉に調味料を加えてよくこねる
- 手で成形する(形は問わない)
- 焼く・炒めるなど、直接火を通す
こねる工程に重点を置くのがつくねの特徴です。
購入時の注意点
スーパーマーケットや肉屋で購入する際の注意点をお伝えします。
冷凍食品売り場では、「鶏団子」として売られることが多いです。これは、冷凍食品は茹でて調理することが前提だからです。
精肉売り場では、「つくね」として売られることが多いです。これは、購入後に焼いて調理することが前提だからです。
私の経験では、同じ商品でも売り場によって呼び方が違うことがよくあります。
おかわりハイボールとつくね。
— ReaLegend (@theme_of_nino) July 12, 2025
つくねさ、だいたい串が2本刺してあるじゃん。
あれって串でつくねを2つに割って食べて欲しいからみたい。
店主の方から教わりました。
知らなかった🤔#焼き鳥#つくね#飲み会#ハイボール pic.twitter.com/Ls62jeh5ng
よくある質問
Q1:レシピで「鶏団子」と書いてあるのに、作り方では「こねる」と書いてある場合はどうすればいい?
A1:レシピでは、完成品の形状を重視して「鶏団子」と表記することが多いです。作り方に「こねる」とあっても、最終的に丸い形にすれば「鶏団子」と呼んで問題ありません。大切なのは、読み手が料理をイメージしやすい呼び方を選ぶことです。
Q2:焼き鳥屋で「鶏団子」を注文したら変に思われる?
A2:焼き鳥屋では一般的に「つくね」と呼ばれているため、「つくね」と注文した方が自然です。ただし、「鶏団子」と言っても理解してもらえるので、大きな問題はありません。店の雰囲気や地域性も考慮して使い分けることをおすすめします。
Q3:子どもに説明する時はどちらを使えばいい?
A3:子どもには「鶏団子」の方が理解しやすいでしょう。「鶏肉で作った丸い団子」という意味が直感的に分かりやすいからです。「つくね」は語源が複雑なので、ある程度理解力が付いてから説明することをおすすめします。
Q4:同じ料理でも呼び方を変えても大丈夫?
A4:はい、大丈夫です。同じ料理でも、注目する部分によって呼び方を変えることは自然なことです。例えば、「手作りつくねを丸めて鶏団子鍋にしよう」という使い方も問題ありません。
「鶏団子」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ
「鶏団子」と「つくね」の違いは、注目するポイントの違いでした。
鶏団子は丸い形状に注目した呼び方で、主に煮る・茹でる料理で使います。 つくねは調理方法(こねる)に注目した呼び方で、主に焼く料理で使います。
どちらも同じ鶏ひき肉を使った料理ですが、使い分けることで、より正確で上品な日本語を話すことができます。
今度料理を作る時や、外食の際には、ぜひこの違いを意識してみてください。きっと料理がより楽しくなるはずです!